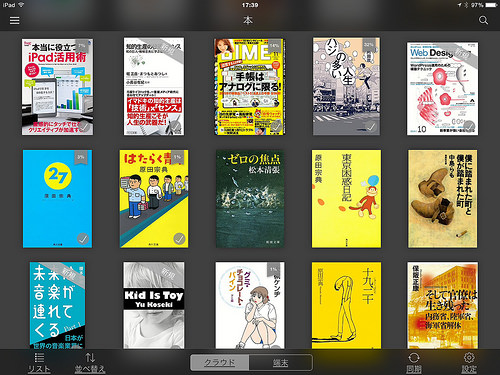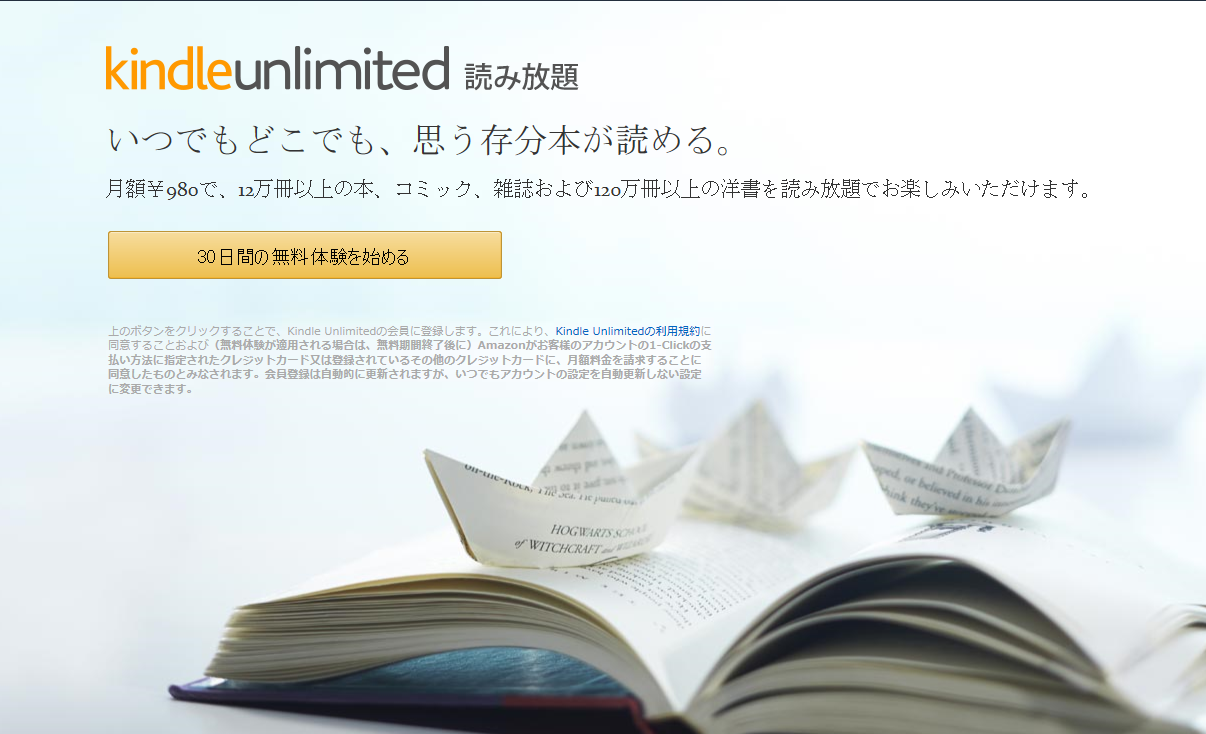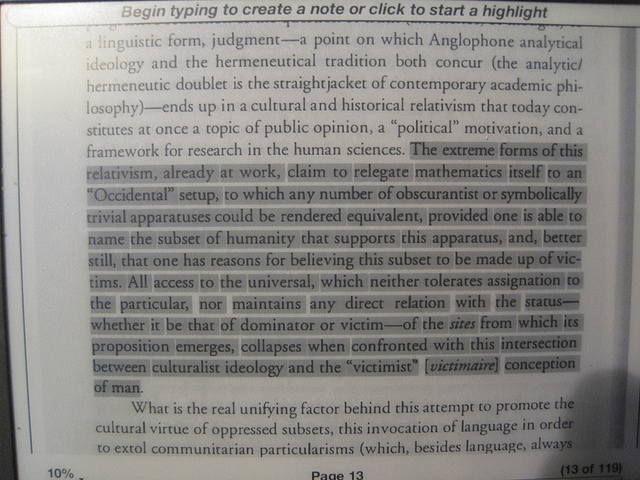電子書籍の店頭販売はナンセンス? 有意義? 電子時代におけるリアル書店の意義とは | nelja.
最近いろいろと社内のゴタゴタがあるようなトーハンさん。
このサービスへの意気込みがあるようですが、実際のところどうかな?と。
というのも、MP3が出てきてiTunesのオープンで音楽のダウンロード販売が本格化したときに、じゃぁCDショップでDL販売するというサービスが立ち上がったか?と。<どこかでひっそりやっててひっそり終わったのかもしれませんが。
また、その時にCDショップでの新しい音楽との出会い、それを支える店員のキュレーションが必要だなんて議論があったか?というと、ボクの知ってる限りとんと聞いたことがございません。
どうしても、販売流通網としての完成された業界としての成り立ち
がCDは弱く、書籍雑誌はしっかりとしたものになっているので、そのあたりの業界の強弱で恣意的に本屋も大事にしなきゃ的な発想から、このようなサービスが出てきているようにしか思えない今日この頃。本屋の文化的な存在としては大切だという認識は十分にありますし、本屋を半日隅から隅までうろついて、思いがけない書籍との出会いにハァハァすることもあります。
が、結構な読書家を自負しているボクがどんな本屋との付き合いをしているかというと、本屋で欲しい本の下見をして本当に面白そうだったら、家でAmazonでポチッとします。
その場で買って重たい本を持って帰る手間も省けるし、送料無料なので本屋で買うのと変わらないので、必然的に本屋はショーケースとしてだけボクの中では成り立っています。
おそらく、電子書籍を本屋で見ることになっても、本屋で確認して家でお気に入りの電書サイトで購入することになるでしょう。
今の電書サイトでは次から次へと本が埋もれてしまって出会いがないとか、キュレーション装置としての役割をなさないとかいうのは、全部電書サイトのインタフェースの問題でしか無いと思ってます。
書店毎のオススメであればそのようなコーナーをサイトに設ければいい話だし、ブラブラでの出会いを演出するのであれば、いまのアバウトなカテゴライズをやめてもっとテーマ毎や詳細なカテゴリ(これは昔のYahooのようなディレクトリサービスの練り直しの方向だと思います。)に電書サイトが頭をもっと使えば良いだけの話のような気がしてなりません。
本を探すための分類ということだけであれば、図書館の書架の配架ように「日本十進分類法」に基づいてカテゴライズするなんてのもオモロイかもしれません。